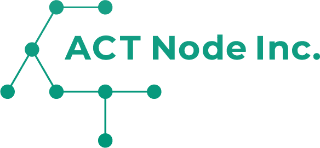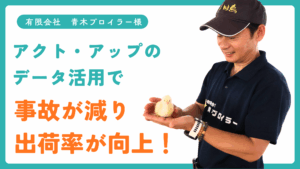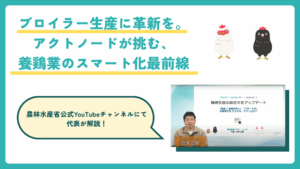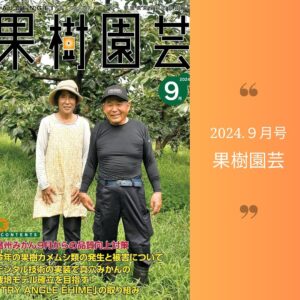こんにちは、アクトノード広報担当のゆうです。前回は弊社代表の百津に、カンボジアでの大規模キャッサバ栽培に携わることになった経緯について話を聞きました。今回は、実際にどのようにして農場を作っていったのかを掘り下げていきます。
「2,000ヘクタール」から「250ヘクタール」へ

当初予定していた2,000haの土地が使えないことがわかり、1年かけて250haの土地を探した百津。2,000haと比べると小さくなりましたが、それでもディズニーランド約5個分。十分すぎる広さです。
百津によると、開墾のプロセスはこんな感じ。
1. 道と水路の整備:ジャングルの木を伐採し、根や石を取り除き、重機が通れるよう道路を整備。合わせて水路も
2. 区画づくり:キャッサバや胡椒などを植える畑を16haごとに分割
3. 畝づくり:キャッサバに合わせた背の高い畝を作り、定植
現代日本においては、当たり前にある道や水路。それを作るところから始めないといけないなんて……!

しかも、現地スタッフに「道をまっすぐ作ってね」と伝えても、大きな石があったら取り除かずに迂回。グネグネの道が完成。さらに、肥料を作物に撒くようお願いしたはずなのに、川に捨てて帰ってくる。キャッサバの収穫作業を依頼したはずが、いつの間にか隣の山に入ってタケノコ狩りを楽しんでいる。そんな小さいトラブルが、多発したそう。
 百津
百津給料をもらったら1週間は休んで働きにこない人もいましたね。欲求に忠実で、合理的ですよね。



合理的といえば、合理的ですが……



日本人とは考え方が違うんですよ。生活のために必死に働くという価値観ではなく、家族と美味しいご飯が食べられればそれだけで幸せという人ばかりなので。日本人に接する感覚で「もっと働け!」と言うと、悪い噂が広がって誰も働きにこなくなることもありました。コミュニケーションの取り方を根本から考えさせられる出来事でした。
カンボジアでの農業を経験したからこそ、日本の農業の良さがわかる


カンボジアの方たちを雇うことで人件費を安くする狙いがあったにも関わらず、実際には作業効率が悪く、最終的には思ったより費用対効果が下がる結果に。
農地の水没などのトラブルも度重なり、思った以上の収益が上がらず、2016年に撤退を決めました。「大規模に生産すれば儲かる、という安直な考えで参入したわけで、今考えれば黒字にならなくて当然ですね」と百津は当時を振り返ります。


とはいえ、カンボジアでの経験から得た学びは大きいそう。



道路や水路がない場所でゼロから農業を始めてみて、日本の生産現場がどれだけ恵まれているかを身をもって痛感しました。農地はまっすぐで、石も根っこも取り除かれていますからね。



先人たちが手を尽くしてくれたから、日本の今の農地があるんですね。



それから、日本人の真面目さ・勤勉さのありがたみを感じました。日本人は指示を出したらその通りに、しっかり考えて動いてくれますから。
カンボジア編おわり