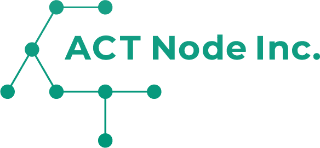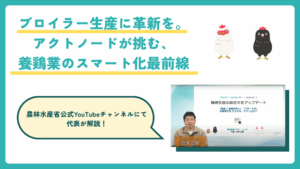2025年の農業センサスが公開されました。ここ5年の変化とトレンドを理解するためにGemini3.0を使った分析結果を公開します。
要旨
2025年2月1日現在で実施された「2025年農林業センサス」の結果(概数値)は、日本農業がかつてない速度で構造転換を遂げていることを浮き彫りにした。本報告書は、農林水産省が公表したデータを基に、農業経営体の劇的な減少、法人化の進展、労働力構造の変化、そして土地利用の集約化について、過去の調査結果との比較を通じて詳細に分析するものである。
今回のセンサスにおける最大の特徴は、農業経営体数が前回調査(2020年)から23.0%減少し、統計開始以来最大の減少幅を記録して82万8千経営体となったことである 。これは、長年「100万経営体」を心理的・構造的な維持ラインとしてきた日本農業が、その閾値を大きく割り込み、新たな局面「産業化フェーズ」へと突入したことを示唆している。
| 重要指標 | 2020年 | 2025年 | 変化 | 意味合い |
| 農業経営体数 | 107.6万 | 82.8万 | -23.0% | 統計開始以来最大の減少幅、100万割れ |
| 法人経営体数 | 3.1万 | 3.3万 | +7.9% | 受け皿としての法人の成長 |
| 平均耕地面積 | 3.1 ha | 3.7 ha | +19.4% | 残存者への急速な農地集積 |
| 大規模層シェア | 44.3% | 51.0% | 過半数 | 20ha以上層が農地の半分を支配 |
一方で、法人経営体数は7.9%増加し、経営耕地面積20ヘクタール以上の大規模経営層が全耕地面積の5割以上を占めるという、歴史的な逆転現象が確認された 。これは、小規模家族経営の離脱と、資本集約的な大規模経営への土地集積が同時に進行していることを意味する。本報告書では、これらのデータが示す「構造的崩壊」と「再構築」の二面性を、分野別・地域別の視点から多角的に論じる。
第1章 2025年センサスの背景とマクロ環境
1.1 調査の意義と歴史的文脈
農林業センサスは、5年ごとに実施される農林業分野の国勢調査であり、国内の生産構造、就業構造、土地利用の実態を把握するための最も基礎的かつ重要な統計である。2025年調査は、戦後の農地改革以降続いてきた「小規模家族経営」を主体とする日本農業のモデルが、実質的に終焉を迎えつつあることをデータとして確定させる歴史的な調査となった。
前回の2020年調査以降、日本農業を取り巻く環境は激変した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによるサプライチェーンの混乱、ウクライナ情勢に端を発する肥料・飼料価格の高騰、急速な円安の進行、そして猛暑や豪雨といった気候変動の激化である。これらの外部要因は、高齢化した農業者に対して「離農」という意思決定を強く迫る圧力として機能した。本センサスの結果は、これらの複合的なストレスが農業構造にどのような不可逆的な変化をもたらしたかを映し出す鏡である。
1.2 マクロトレンド:加速する縮小均衡
2025年センサスの結果を俯瞰すると、日本農業全体が「縮小」しながら「密度を高める」というプロセスにあることが読み取れる。農業経営体数の減少率が過去最大の23.0%に達したことは、単なる自然減ではなく、構造的な淘汰が加速していることを示している 。
過去のセンサスにおいて、経営体数の減少率は概ね10%〜15%台で推移してきた。今回、この減少率が一気に20%台後半へと跳ね上がった背景には、コストプッシュインフレと気象災害が、限界的な経営を行っていた小規模層の退出を決定的なものにした事実がある。特に、資材高騰の影響を価格転嫁しにくい小規模稲作農家層において、この傾向は顕著であったと推察される。
▼ 図表1:農業経営体数の減少トレンド 過去の減少率と比較しても、今回の「23.0%減」という数字がいかに衝撃的であるかが分かります。
| 調査年 | 農業経営体数 | 減少数(前回比) | 減少率 | 背景 |
| 2015年 | 137.7万 | – | – | |
| 2020年 | 107.6万 | -30.1万 | -21.9% | 高齢化の進行 |
| 2025年 | 82.8万 | -24.7万 | -23.0% | 資材高騰、猛暑、後期高齢化 |
第2章 農業経営体の構造変化:個人的経営の崩壊と法人の台頭
本章では、農業生産の担い手である「農業経営体」の数と質の変化について詳細に分析する。
2.1 経営体数の激減と「100万割れ」の衝撃
2025年2月1日現在の農業経営体数は82万8千経営体となり、2020年の107万6千経営体から約24万7千経営体(23.0%)減少した 。この減少数は、地方都市の人口に匹敵する規模の生産主体がわずか5年間で消滅したことを意味する。
特筆すべきは、減少のスピードが加速している点である。2015年から2020年の減少幅と比較しても、今回の減少率は際立って高い。これは、団塊の世代(1947-1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となり、肉体的な限界や後継者不在を理由に営農継続を断念するケースが急増した「2025年問題」が、統計上の現実として顕在化した結果である。
特筆すべきは、個人経営体(家族経営)の激減と、法人経営体の着実な増加という対照的な動きです。
▼ 図表2:経営形態別の増減内訳 個人経営体が約25万も消滅する一方で、法人は2,000経営体増加しました。
| 経営形態 | 2020年 | 2025年 | 増減数 | 増減率 | 傾向 |
| 総数 | 107.6万 | 82.8万 | -24.7万 | -23.0% | 激減 |
| 個人経営体 | 103.7万 | 78.9万 | -24.8万 | -23.9% | 離農加速 |
| 団体経営体 | 3.8万 | 3.9万 | +0.1万 | +2.9% | 微増 |
| (うち法人) | 3.1万 | 3.3万 | +0.2万 | +7.9% | 成長 |
このデータは、消滅した約120の個人経営体の機能を、わずか1つの新規・既存法人がカバーしなければならないという「受け皿不足」の現実を示唆しています。
2.2 個人経営体の退出と法人経営体の成長
経営形態別に見ると、構造変化のコントラストはより鮮明となる。
▼ 図表3:経営体数の変化
| 経営形態 | 2020年(概数) | 2025年(概数) | 増減率 | 傾向 |
| 農業経営体総数 | 1,075,700 | 828,000 | -23.0% | 大幅減 1 |
| 法人経営体 | 31,000 | 33,000 | +7.9% | 増加 1 |
| 個人経営体 | 1,044,700 | 795,000* | -23.9%* | 大幅減(推計) |
(※個人経営体数は総数と法人数からの推計値)
法人経営体数は3万3千経営体となり、前回から7.9%増加した 1。総数が激減する中での法人の増加は、日本農業の担い手が「家業」から「企業」へと質的に転換していることを示している。特に東北地域では、法人経営体が8.3%増加しており、全国平均を上回るペースで組織化が進んでいる 3。これは、米どころである東北において、集落営農の法人化や、離農者の農地を受け入れるための受け皿としての法人設立が進んでいることを示唆している。
しかし、ここで注視すべきは「代替率」の低さである。24万7千の経営体が消滅したのに対し、増加した法人はわずか2千経営体程度に過ぎない。単純計算で、消滅した約120の個人経営体の農地や生産機能を、1つの新規・既存法人がカバーしなければならない計算となる。この圧倒的な「受け皿不足」が、後述する耕作放棄地の問題や地域農業の空洞化リスクに直結している。
2.3 規模拡大の進展と二極化
1経営体当たりの経営耕地面積は3.7ヘクタールとなり、5年前から0.6ヘクタール(約19%)増加した 。この規模拡大のペースも過去にない速さである。
東北地域では1経営体当たり4.0ヘクタールに達し、0.8ヘクタールの増加を記録している 。離農が加速したことで、残存する経営体(サバイバー)に農地が急速に集積している構図が見て取れる。農地中間管理事業(農地バンク)などの政策的後押しも相まって、意欲ある担い手への農地集約が進んでいることは、生産性の向上という観点からはポジティブな側面である
▼ 図表4:1経営体当たり経営耕地面積の推移
| 項目 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 10年間の変化 |
| 全国平均 | 2.5 ha | 3.1 ha | 3.7 ha | +1.2 ha |
| 北海道 | – | 30.2 ha | 34.5 ha | 大規模化がさらに進行 |
| 都府県 | – | 2.2 ha | 2.6 ha | 小規模ながら集積進む |
しかし、これは「自然な成長」というよりは、「周囲の撤退による受動的な拡大」の側面も強い。3.7ヘクタールという平均値は、依然として国際的な穀物生産の基準から見れば小規模であり、コスト競争力を十分に発揮できる規模とは言い難い。
第3章 労働力と人口動態:平均年齢低下のパラドックス
農業従事者の高齢化は長年の課題であるが、2025年センサスでは特異な現象が観測された。
3.1 基幹的農業従事者の減少と平均年齢の変化
基幹的農業従事者の平均年齢は67.6歳となり、前回から0.2歳低下した 。平均年齢の低下は、比較可能な1995年以降で初めての現象である。
一般に平均年齢の低下は、若年層の参入増加(若返り)を意味すると解釈されがちである。しかし、今回の低下は「ポジティブな若返り」ではない。分析記事が指摘するように、これは「高齢者層の離農・廃業が加速した」結果に他ならない 。
▼ 図表5:基幹的農業従事者の変化
| 項目 | 2020年 | 2025年 | 変化 | 要因 |
| 従事者数 | 136.3万人 | 102.1万人 | -34.2万人 (-25.1%) | 過去最大の減少率 |
| 平均年齢 | 67.8歳 | 67.6歳 | -0.2歳 | 高齢層の退出による低下 |
| 65歳以上割合 | 69.6% | 69.5% | -0.1pt | 高止まり |
具体的には、80代以上の超高齢農業者が、死亡や身体機能の低下、あるいは猛暑などの過酷な環境に耐えられずに大量にリタイアしたことで、統計上の平均値が押し下げられたという「計算上のマジック」である。65歳以上の構成割合が0.1ポイント減の69.5%となったこと も、この仮説を裏付けている。つまり、若者が増えたのではなく、「最も高齢な層がいなくなった」のである。
3.2 地域別の深刻度:山口県の事例
全国平均での「若返り」という錯覚に対し、地域別のデータはより深刻な現実を突きつけている。中山間地域を多く抱える山口県では、平均年齢が72.5歳となり、前回(72.3歳)から上昇して全国最高齢となった 。
- 山口県の平均年齢: 72.5歳(全国最高齢、前回比+0.2歳)
- 65歳以上の割合: 84.8%(個人経営体の従事者)
山口県における個人経営体のうち、65歳以上の高齢者は全体の84.8%を占めている 。これは、平地農業が中心で法人化が進む地域(平均年齢が下がる傾向にある地域)と、条件不利地が多く担い手交代が進まない地域との間で、人口動態の二極化が進行していることを示している。後者の地域では、現在の70代・80代が引退した後に農業を担う層が物理的に存在せず、集落機能の維持そのものが危機的状況にある。
3.3 労働力不足とデータ活用農業への転換
絶対的な労働力人口が減少する中で、残された経営体が生産を維持・拡大するためには、テクノロジーによる省力化が不可欠となっている。2020年センサスの時点で既にデータを活用した農業経営体は18万を超えていたが 、2025年の状況下では、スマート農業は「先進的な取り組み」から「生存のための必須条件」へと位置づけが変わっている。
特に、1経営体当たりの面積が拡大する中で、限られた人員で広大な圃場を管理するためには、自動操舵トラクターや水管理システム、ドローンなどの導入が不可避となる。三菱総合研究所のレポートが示唆するように、生産者の構造改革と省力化技術の普及は、労働力減少を補う唯一の解となりつつある 。
第4章 土地利用の構造転換:5割を超える集積と荒廃のリスク
土地利用の面では、日本の農地制度の歴史における転換点とも言えるデータが示された。
4.1 大規模層への農地支配権のシフト
経営耕地面積20ヘクタール以上の農業経営体が利用する農地面積のシェアが、初めて5割を超えた 。これは、日本農業の過半が、もはや小規模家族経営ではなく、大規模経営体によって管理されていることを意味する。
▼ 図表5:20ha以上経営体の農地シェア推移
| 年次 | シェア(占有率) | 状況 |
| 2015年 | 37.5% | |
| 2020年 | 44.3% | |
| 2025年 | 51.0% | 初めて過半数を超える |
「20ヘクタール」というラインは、日本の土地利用型農業において、一定の資本装備と雇用労働力を必要とする「企業的経営」の閾値である。この層が農地の過半を握ったことは、農業政策の対象を「全農家」から「産業としての農業経営体」へと完全にシフトさせる根拠となり得る。
4.2 耕地面積の減少と荒廃農地の拡大
一方で、利用される農地の総量は確実に減少している。田(水田)の耕地面積は、令和5年(2023年)から令和7年(2025年)にかけて減少傾向が続いており、2025年の田耕地面積は230万ヘクタール(前年比1万9千ヘクタール減)となった 。
- 田(水田)の面積: 230万ha(前年比1.9万ha減)
この減少の内訳を見ると、東北で4,900ヘクタール、九州で2,600ヘクタールの減少が記録されている 。ここで重要なのは、「離農した経営体の農地がすべて大規模経営体に継承されているわけではない」という点である。条件の良い平地の農地は大規模層に集積される(これが20ha以上層のシェア拡大に寄与)一方で、条件の悪い農地や、まとまりのない分散した農地は、受け手が現れずに耕作放棄(荒廃農地)化している。
荒廃農地の発生は、病害虫の発生源となったり、鳥獣被害を助長したりするなど、地域全体の生産環境を悪化させる。23%の経営体が消滅した今、その跡地管理を誰が担うのかは、食料生産の問題を超えて、国土保全の深刻な課題となっている。
第5章 分野別生産構造の変化:米から高収益作物への静かなるシフト
生産品目(部門)別の構成割合の変化からは、農業経営体の生存戦略が読み取れる。
5.1 稲作の低下と園芸の伸長
農産物販売金額1位の部門別構成割合において、稲作は54.4%となり、前回から1.1ポイント低下した 。依然として過半数を占めるものの、その割合は着実に低下している。
稲作部門の低下要因は、主に以下の2点に集約される。
米消費の減少と転作: 国内の主食用米需要が減少する中、飼料用米や麦・大豆、あるいは野菜への転換が政策的に推進されてきた。
小規模層の退出: 稲作は他の品目に比べて機械化が進んでおり、兼業や高齢者でも取り組みやすい反面、収益性が低く、小規模では資材高騰の影響を吸収できない。今回の23%の経営体減少の主たる部分は、この小規模稲作層の退出であると考えられる。
▼ 図表6:農産物販売金額1位部門の構成割合変化
| 部門 | 構成割合 (2025) | 前回比 | 分析 |
| 稲作 | 54.4% | -1.1 pt | 小規模層の退出、転作の進展 |
| 果樹類 | 上昇 | +1.1 pt | 輸出需要、高単価品目へのシフト |
| 施設野菜 | 上昇 | +0.5 pt | 環境制御による安定生産志向 |
しかし、東北地域での法人増加 が示すように、稲作部門内部では「小規模多数」から「大規模法人による集約生産」への質的転換が進んでいる。生き残った稲作経営体は、数こそ減っているものの、1経営体当たりの作付面積を拡大し、生産コストの低減を図っている。
5.2 園芸(果樹・施設野菜):高付加価値化への志向
対照的に、構成割合を伸ばしたのが園芸部門である。
- 果樹類: 構成割合が前回比1.1ポイント上昇 。
- 施設野菜: 構成割合が前回比0.5ポイント上昇 。
経営体総数が減少する中で、これらの部門の割合が上昇したことは、農業経営における「選択と集中」が進んでいることを示唆する。 果樹部門の上昇は興味深い現象である。果樹栽培は労働集約的であり機械化が難しいため、本来であれば高齢化の影響を受けやすい。しかし、シャインマスカットや輸出用リンゴ、柑橘類などの高単価品目への需要が高まっており、収益性の高さが経営維持のモチベーションになっていると考えられる。また、果樹は永年作物であり、一度植えると改植や廃棄にコストがかかるため、簡単には離農できないという「資産の固定性」も、割合維持(相対的上昇)の一因かもしれない。
施設野菜の上昇は、より明確な経営戦略の結果である。施設園芸は環境制御技術(スマート農業)との親和性が高く、天候リスクを軽減しながら、年間を通じて安定した収益を上げることができる。資材高騰下において、価格転嫁が比較的容易な高付加価値野菜へのシフトが進んでいることが推察される。
5.3 地域別の生産構造:北海道の特異性
地域別の視点では、北海道が依然として独自の構造を維持している。北海道の農業経営体数は29,025経営体で16.9%減少したが、減少率は全国平均(23.0%)よりも緩やかである 。
北海道では、畑作(小麦、ジャガイモ、甜菜、豆類)や酪農といった、土地利用型かつ資本集約的な農業が主体である。法人経営体の割合も高く、既に大規模化が完了している経営体も多いため、本州以南のような「小規模層の雪崩的離脱」の影響が相対的に小さい。しかし、それでも16.9%の減少は深刻であり、広大な大地を少数の経営体で支える限界が近づいていることに変わりはない。
第6章 結論:2030年に向けた課題
2025年農林業センサスは、日本農業が「小規模・家族・兼業」という昭和モデルから、「大規模・法人・専業」という令和モデルへと、不可逆的に移行したことを証明した。
6.1 分析の総括
- 構造改革の強制的な完了: 長年、政策が目指してきた「担い手への農地集積」は、政策の効果というよりも、高齢化とコスト高による「強制的な淘汰」によって急速に達成されつつある。20ha以上層が農地の過半を占める現状は、農業の産業化の進展を示す一方で、地域社会の維持という観点からは、農村人口の希薄化という重い課題を突きつけている。
- 「空白」の拡大: 経営体の減少数(約25万)と法人の増加数(約2千)のギャップはあまりにも大きい。この「埋められない空白」は、耕作放棄地の拡大や、水路・農道などの地域資源管理の崩壊として、今後数年でより顕著に現れるだろう。
- 生存戦略としての高付加価値化: 稲作から果樹・施設野菜への相対的なシフトは、規模拡大だけでは生き残れない中小規模層が、質的向上(高単価化)に活路を見出している証左である。
6.2 将来展望と提言
今後の5年間、次回の2030年センサスに向けて、日本農業は以下の課題に直面する。
- 「受け皿」の強化: 離農は今後も続く。受け皿となる法人経営体の経営管理能力(マネジメント力)を強化し、1社で100ヘクタール、200ヘクタールを管理できるような「メガ・ファーマー」の育成が急務である。同時に、これら法人が地域社会と融和し、地域のインフラ管理を担えるような仕組みづくり(日本型直接支払制度の再構築など)が必要となる。
- スマート農業の実装: 労働力の絶対数が不足する中で、平均年齢67.6歳の現場を回すには、自動化技術の社会実装が待ったなしである。データ共有基盤の整備や、高額な機械をシェアリングするサービスの普及が鍵となる。
- 多様な担い手の確保: 家族経営の継承だけでなく、企業参入や「半農半X」のような多様な関わり方を許容し、農業人口の裾野を広げる努力も並行して必要である。
2025年センサスの結果は、危機的であると同時に、日本農業が効率的な産業へと脱皮する最後のチャンスを示しているとも言える。このデータを直視し、感情論ではない科学的かつ冷徹な経営・政策判断が求められている。
参考文献・出典